外国人が日本に在留して就労するためには就労系の在留資格が必要となります。
この就労系在留資格の中で代表的なものが「技術・人文知識・国際業務」になります。
「技術・人文知識・国際業務」でできる活動とは
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動内容は入管法で次のように定められています。
具体例としては、電気や機械系のエンジニア、SEなどのコンピューター関連の仕事、経理や貿易などの事務職、マーケティング業務従事者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等のいわゆるホワイトカラーの頭脳労働がこの在留資格の活動に当たります。
また、上記の「契約」は、雇用のほか、委任契約、請負契約、業務委託契約も含みます。常勤、正社員だけではなく、非常勤職員やアルバイトも含みます(ただし在留期間は短くなります)。
人手不足解消のための単純労働や「技能実習」「特定技能」に当たるような活動は、この在留資格には該当しないので注意が必要です。
なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月となっています。
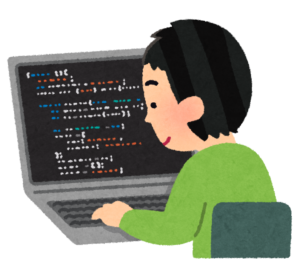
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請するためには、申請者の学歴や実務経験など、以下のとおり、要件が定められています。
1.学歴・実務経験
◆技術・人文知識の場合
(エンジニア、コンピューター関連業務、経理、マーケティングなど)
申請人が自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、必要な技術または知識を取得していること
ア その技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し(海外の大学を含む)、またはこれと同等以上の教育を受けたこと(短大・準学士など)
なお、「関連する科目」については、専攻した科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく、関連していればよいとされ、比較的緩やかに判断されます(卒業証明書、成績証明書などで実際に履修した科目などを確認します)。
イ その技術または知能に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
なお、「関連する科目」については、大学とは異なり専門科目と従事しようとする業務との間に相当な関連性が必要とされています。
※1 その修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件(専門士、高度専門士)に該当する場合に限ります。
※2 外国の専門学校は含まれません。
※3 外国人留学生の割合が2分の1以下や、就職率90%以上などの認定専門学校については、関連性について大学同様に柔軟に判断されます
ウ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
これは、過去の勤務先発行の在職証明書で立証できることが必要になります。
◆国際業務の場合
(翻訳、通訳、私企業の語学教師、デザイナー、貿易業務など)
申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること
ア 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これに類似する業務に従事すること
イ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
これは、過去の勤務先発行の在職証明書で立証できることが必要になります。
なお、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は問われません(大学の専攻も問われません)。

2.報酬額
申請人である外国人が、企業等の所属機関で日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
これは、外国人に対する不当な差別は禁止し、同じ会社に勤めているのであれば日本人と同等の給料を支払ってくださいという趣旨です。外国人だから日本人より安く雇用できるということにはなりません。
当然、報酬額が所属機関の所在する都道府県の法定最低賃金額を下回っていれば申請は不許可となる可能性は大きいです。
3.会社等の経営状況
申請者の勤め先の会社等の経営状態が安定していることが必要になります。
大幅な赤字決算だと、外国人社員に給料が払えないのではないかと判断されてしまい審査が厳しくなります。経営状態は決算書類を提出して証明することになります。
ただし、今は赤字であっても事業計画書を示して将来的には黒字化できる旨の説明ができれば審査が通る可能性はあります。
新設会社で決算書類を出せない場合も、事業計画書を提出する必要があります。
4.雇用の必要性
出入国在留管理庁が「技術・人文知識・国際業務」の審査をするに当たっては、勤務先で申請者の本国に関わる業務を行うかなど雇用の必要性も確認されます。
雇用の必要性は主に、採用理由書で確認されます。
採用理由書では、内定を出した企業等が外国人をどこに配属するのか、どのような職種に従事させるのか、必要な専門知識は何か、日本語能力はどれくらいか、本国など海外との接点はあるかなど、どうしてその外国人が必要なのかを説明することになります。
5.犯罪歴
「技術・人文知識・国際業務」に限ったものではないですが、外国人が日本に上陸し在留資格を得るには、外国人本人に前科(1年以上の懲役もしくは禁錮等)のないことが必要になります。
「技術・人文知識・国際業務」で判断に迷う職種について
①飲食業
飲食業界の場合、仕事内容が、総務部門やマーケティングの仕事など事務系の職種であれば在留資格は取れる可能性が大きいです。
ただし、ある程度の企業規模でなければ外国人採用の必要性が認められないので注意が必要です。
なお、ホール係、レジ、調理では単純労働とみなされ在留資格は取れません。
②ホテル業
ホテル業の場合、外国人客を対象にしたマーケティング、経営企画、総務、経理などであれば在留資格は取れる可能性が大きいです。
ホテル内のレストランでの接客・調理、客室清掃、ドアマンなどは単純労働とみなされ在留資格は取れません。
③製造業・建設業
製造業・建設業の場合、事務部門、技術部門であれば在留資格が取れる可能性は大きいです。
事務であれば、海外との通訳・翻訳、人事総務、会計、マーケティングなど、技術部門であれば、製品開発、品質管理、技術教育、設計、技術開発などが該当します。
工場・建設現場などでの現場作業は単純労働とみなされ在留資格は取れません。
フリーランスで「技術・人文知識・国際業務」は取れるか
フリーランス(個人事業主)でも、ITエンジニアや通訳者・翻訳者などで複数社との業務契約があり、契約金額や契約期間などで継続性や安定性が認められれば「技術・人文知識・国際業務」で在留資格を取れる可能性があります。
以上が在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての概要になります。参考になればうれしいです。